プロレスラーの長州力さんが2019年6月26日、引退しました。
最初にお断りしておきますが、私は「プロレスラー長州力」の熱烈なファンでも、信者でもありません。さらに言うと、1998年に現役を一度引退して、東京ドームの引退記念興業までやっておきながら(理由はどうあれ)復帰したのがどうにもイヤで、今でもあのまま引退して欲しかったと思っています(シニアリーグでのエキシビジョン的な試合は観たいけど)。
ただ・・・、長州力が”革命戦士”としてブレイクする前、中堅どころでくすぶり、伸び悩んでいた時期から観ていたからこそ、思うところがあります。
私が長州力から学んだことは、”仕事との向き合い方で、人はいつでも変われる”ということです。
今回はそのあたりを、プロレスが別に好きじゃない、長州力なんて知らない人でもわかるように、いまの自分の仕事との向き合い方に悩んでる、という人向けに・・・というとエラソーだな。・・・自分に対して、書こうと思います。

■”ブレイク”前の長州力とは?
長州力という選手は、アマレスでオリンピック代表(’73 ミュンヘン五輪 韓国代表)になったレベルのアスリートです。アマチュア時代の彼を知る人たちは、口をそろえて「強かった」「すごかった」と言います。
そして彼は新日本プロレスという、アントニオ猪木が社長を務める会社にスカウトされて、専修大学卒業後、1974(昭和49)年にプロレスラーになりました。
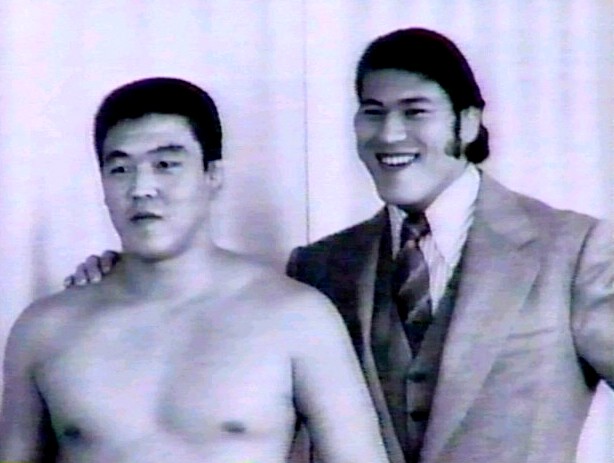
期待もされました。吉田光男から”長州力”というリングネームをファン公募して付けてもらい(実は猪木が命名w)、猪木の師であるカール ゴッチから”サソリ固め”という必殺技も伝授され、海外にも3回も武者修行に行き、当時のナンバー2である副社長で元柔道日本一、”世界の荒鷲”坂口征二とのコンビで、「北米タッグ」というチャンピオンベルトも巻きました。

格付け、でいえば猪木、坂口、藤波に次ぐ、4番手にはいたのです。
しかし長州には、圧倒的に「ファンの支持」がありませんでした。簡単に言うと「人気がない」のです。
理由はただ一つ、彼の試合が面白くなくて、応援する気にならない超・地味な選手だったからです。見た目も小柄でずんぐりむっくり。手足も短く、髪形も七三分けかパンチパーマ。ルックスも・・・。典型的な、中堅どころのモブ役レスラーです。
持ち味は「パワーファイト」。要は「華麗な技よりも力が強い」というタイプなのですが、190㎝を超える選手がゴロゴロいる当時のプロレス界で、180㎝そこそこの彼は小さい部類です。小さい選手は、「スピード」とか「テクニック」で魅せるのですが、彼にはそれがありません。要は彼につけられた「パワーファイター」という呼び名は、ほかに取り柄がない、という意味だったのです(実際、彼のパワーは凄いのですが、もっと凄い選手がほかにたくさんいた、という意味です)。
でも、ファンが彼を応援しない理由は、没個性やイケてないルックス、が理由ではありませんでした。
■「プロレスラーという仕事」の仕組み
プロレスというジャンルは、ほかのプロスポーツ競技と比べて、異質な点がかなりあります。中でも最も異質なのが、「強ければ名選手ではない」、という点です。
本場アメリカでも日本でもメキシコでも、「もっとも観客を動員できる選手=人気のある選手」がスターで、金も稼げるのです。日本は団体という会社所属の給料(年俸)制ですが、海外では1試合いくらの歩合で、その日の興行収益によってギャラが変動するのが、本来の仕組みです。
そのため、「実は大して強くないけど人気があるレスラー」や「強いけどそれを隠して卑怯な真似をして観客のヒート(興奮)を買うのが上手なレスラー」などなど、客を会場に呼べて、チケットが売れる「観客動員力がある」のが名レスラー、人気レスラーなのです(そしてチャンピオンという役割は「いざとなったら実力でもねじ伏せられて、普段は各地の人気選手にスレスレのところで負けないようにベルトを防衛し続ける」という役割が期待されます。「今回は惜しかったけど、次は挑戦者が勝つかもしれない」というのがまた次回、興行に来てもらえる大事な要素なのです)
プロレスは毎試合、ただ試合をして勝てばいいのではなく、互いにいいところを引き出し合って、観客を満足させ、あー面白かった(興奮した、悔しかった)、また観にこよう!、と思わせないとならないワケです。
プロレスラー長州力は、この点が納得がいかなかったのでしょう。根っからの体育会系、アマレスエリートでアスリート気質だった彼からすると、そんな演劇みたいなのスポーツと言えるのか?と。勝ち負けじゃない要素で、それも個性とかキャラとか、敢えて技を受けて、もっとアピールして観客を魅了しろとか、なんなんだよそれ?しかも観客は、オレのアスリートとしての技術を見分ける力などない素人ばかり。なんでそんな連中に媚びてまで、金を稼がなくちゃならないんだ、冗談じゃない、やってられるか!と思うのも、無理はありません。
彼はプロレスという、自分が選んだ仕事に誇りどころか、やりがいが感じられなかったのでしょう。
■「オレには向いてない」仕事
長州力のボス、社長のアントニオ猪木はプロレスが天才的にうまいレスラーでした。
「神様」カール ゴッチ仕込みのテクニックと、「鉄人」ルー テーズに倣ったプロとしての華や魅せ方、そして力道山からは業界を背負う”スター”としてのオーラと、本気で怒るケンカ殺法の凄みを学び取り、それをミックスさせて世界でも稀な”燃える闘魂””ストロングスタイル”で観客を魅了し続ける、プロレスの天才でした。プロレス界でもアントニオ猪木の人気が高いのは、ハラハラドキドキさせられて、テクニックで唸らされて、誰が相手でも決して怯まない、そのスタミナと技術に加えて、精神力=闘魂でした。
全盛期のアントニオ猪木の凄さは、プロレスが好きじゃない、むしろバカにしている人までもが、猪木のプロレスは何かが違う、と本気にさせる、魔性の力でした。それは、ほかのレスラーとは違う、見せかけではない”本気の怒りや強さ、苦しみ、やられっぷり、そしてなんだか奥底にある哀しみ”が3階席にいる、あるいはTV越しにでも、観ている人にビンビンに伝わる、「説得力」でした。
長州力はおそらくこの時期、プロレスラーになったことを後悔していたと思います。
”オレはプロレスラーに憧れて、なりたくてなったわけじゃない。あの人(猪木)みたいに自分に酔いしれるようなマネはできないし、ほかの選手みたいにカッコだけとか、観客に媚びたくもない。どうすれば売れるとか、そんなこと考えたくもない。この仕事は自分には向いていない・・・”
それどころか、嫌悪感すら抱いて、プロレスラーになった自分を恥とさえ、感じていたような気がします。
しかし、ほかに選択肢はありませんでした。いまさらサラリーマンになってデスクワークしたり、商売をして人に頭を下げるようなのも向いていない。アマレス一筋で、ほかのスポーツで金が稼げるとも思えない。
彼にとってプロレスは「仕事」でした。仕事は金を稼ぐためのものです。ささやかでもいい、できたら人より少し豊かに暮らすための、手段です。これは間違っていません。その通りです。ただし、ここから2つの道があります。
「仕事だからなんとなくやり過ごして、イヤなことがあっても我慢して、そこそこ頑張ってるように見えてればいいや」と、
「どうせ仕事するなら打ち込んで、人よりできるようになって、極めてやろう」という考え方です。
”ブレイク”前の長州力は、明らかに前者でした。そしてそれは、観客に、ましてや当時、小学生だった私にまで、伝わってしまっていたのです。
プロレスはタイツとシューズだけの裸に近い姿で、360°観客に囲まれた中で、10分も30分、時には1時間近く「試合」します。
その中では、見てくれだけのやる気とか頑張りは、すぐにメッキがはがれてしまうのです。観客はバカではありません。アレは痛がったり怒ってるフリしてるだけだな、淡々と仕事をこなしている人、というのは、すぐわかるものなのです。
私は当時の長州力の試合を観るたびに、「この選手は、なにがやりたいのかさっぱりわからない、やる気あるのかな?プロレス嫌いなのかな?」と感じていました。長州力が手を抜いていたというワケではありません。彼なりに、黙々と試合していました。でも、いくら技を出そうが、勝とうが負けようが、”伝わってくるもの”が何もないのです。”必死”じゃなく、淡々としているのです。
彼が人気がなく、誰も熱心に応援しないのは、テクニックとかルックスとかではなく、それこそが理由だった気がします。
そしてそんなレスラーは、プロレス界にも山ほどいます。アメリカでもメキシコでも、そんな「仕事をこなす」レスラーたちと、仕事後にうまいビールを飲んで、これが気楽でいいのかも、と感じて、日本に帰りたくなかった、と言っていました。
■オレはオマエの噛ませ犬じゃない!
そんな鳴かず飛ばずの長州力が、メキシコ遠征から帰国した直後のTVマッチで、藤波辰巳(現:辰爾)に噛みついたのが、すべての始まりでした。

カンタンに説明すると、長州力が叩き上げの、2つ歳下の先輩スター超人気選手であるタッグチーム仲間の藤波に「オレはお前より強いのに、なんで下に扱われなくちゃならいんだ!」と試合中に不満を爆発させて、試合そっちのけで仲間割れして大ゲンカしたのが、テレビ朝日金曜夜8時のゴールデンタイムに全国生中継された、という事件です。
なぜあの長州力が、急に本気になったのか?はいまだに謎です。当人たちは決して語りませんが、なんらか「猪木からの示唆」があったのは間違いないようです。直接的に「今夜の試合で藤波に噛みつけ」とかではなく、「オマエはこのまま終わるつもりでいるのか?」というようなニュアンスのようです。「どうせなら、一回本気でやってみろよ」的なことなんじゃないかと思います。
ハッキリしている事実は、ここからの長州力は、まったくの別人になった、ということです。
本気で怒り、苦しみ、悩みぬいた末の感情の爆発だったからこそ、観客は待ってました!とばかりに指示しました。あの地味だった長州が本気で怒ってるぞ、それも相手は同じ会社の藤波だぞ。こりゃ面白いぞ、どっちが強いか、やれやれ!って感じです。そして試合でも、これまでとは打って変わって、鬼気迫るような迫力が全身から感じられました。入場から退場まで、それこそ蹴りの一発から投げから、殺気に包まれてものすごいド迫力、威圧感なのです。そう見せよう、とかではなくて、本気と書いてマジ、というのが、誰から見ても明らかでした。

オレはこの賭けに負けたらプロレス辞める!大げさに言えば、これに負けたら死んでやる!くらいの本気度だった印象です。自分の所属する団体の人気選手にケンカを討って、負けたらなに言われるか・・・切羽詰まった感じが、迫力につながりました。

そんな選手、応援しないわけはありません。瞬く間に長州力は、トップレスラーに上り詰めました。観客も視聴者も、彼の”本気”を熱烈に支持しました。会社や学校で燻っている人々が「自分にはできないことを、この男ならやってくれるんじゃないか」とシンパシーと憧れを抱き、長州力はそれにも後押しされて、押しも押されぬ大スターになりました。
実況の古舘伊知郎アナウンサーは、そんな彼を下剋上を起こした放浪の若獅子、そして”革命戦士”と名付けました。やがて猪木政権を打倒する討幕の志士、”維新軍団”が結成され、そのリーダーとなります。

そして遂には団体を飛び出してライバル団体、ジャイアント馬場率いる全日本プロレスに殴り込みます。彼のプロレスは”叩き潰すプロレス”と呼ばれました。そしてそこで、同じ境遇でくすぶっていた元大相撲の天龍源一郎と戦って、彼もまた革命戦士となる・・・という大河ドラマが続いていくのです。

長州力は寡黙ですが、名コピーライターでもありました。「オレはオマエの噛ませ犬じゃない」「オレの人生にも一度くらい、幸せなことがあってもいいだろう」「オマエにはあの非常ベルが聴こえないのか」「俺たちの時代だ」などなど・・・
そして長州力はずっとアントニオ猪木のそばにいたわけでもなく、時には痛烈な言葉で(人間性までも含めて)批判も繰り返して、その呪縛から逃れよう、ともしてきた選手です。
「そういうストーリーでしょ」と言うとそんな話ではありません。プロレス界の設定なんて雑なものです。その時々の着想や行動は、プロレスラー自身の危機感や焦燥感、そしてジェラシーと、観客の反応から生まれるリアルです。そこが日本の(昭和の)プロレスの面白いところなのです。
そんなプロレスを子供のころから観続けていた私は、知らぬ間に仕事に対して、「どうせやるならそれなり、じゃなくて徹底してやるべきだよな」と考えるようになっていました。淡々と、流していた自分の仕事に”本気”で向き合い、やりたくない、と思っていたことを”必死に”やり、そんな彼を手のひらを反すかのごとく熱狂的に支持する観客。
そしてそれに応えて、活き活きと躍動する中で顔つきも変わり、カッコよく観えるのがほんとに不思議でした。覚悟を決めた人間のカッコよさですね。「やりがい」ってものは、本気で取り組んで初めて手に入るものなのです。周囲のせいにしてばかりで本気にならなければ、どんな仕事だって面白くもクソもない、ただの作業者なのです。
■長州力にとっての「プロレス」とは?
長州力の言語感覚は不思議なセンスがあり(滑舌の悪さとは別の話です)、自慢やウソはつきませんが、ほんとのところは決して言わない性質です。自伝も読み、インタビューもかなりたくさん観たり読んだりしましたが、本当のところ、「長州力にとってのプロレスとは何だったのか?(いま、どう思っているのか?)」については、明確に発言していません。
「言っても伝わらないよ」と思っている、だから本当のところを語らない、そんな気がします。
長州力は後年、興行を取り仕切る「現場監督」となってから、一つの指針を明確にしました。それは、「オレは練習しないヤツは認めない」ということ。「プロレスは華があれば、客が呼べたらそれでいい」ということも知っていながらも、そこはやはり長州力の、アスリートとしての意地だったと思います。もちろんそれは、「プロレスこそ最強である」と繰り返し世間と戦ってきたアントニオ猪木も同じですが、猪木以上に長州は、執拗にそれを選手に求めました。
たとえ相手が元横綱の北尾光司であっても、元柔道日本一の小川直也であっても、エースでIWGPチャンプの橋本真也であっても、です。それで衝突して、クビにするまで徹底するのが、長州力でした。だからこそ、長州力にだけは最もプロレスチックな「引退からの現役カムバック」(しかも大仁田厚相手)は、やめて欲しかったのです・・・しつこいですが。
6月26日引退試合の後、長州力が控室で記者からの問いかけでもなく独りで語りだしたのは、アントニオ猪木のことでした。この中にかなり、”長州力にとってのプロレス”が初めて語られているので、紹介します。

「やっぱり、一番最大、気持ちの中で残っているのはやっぱり(アントニオ)猪木会長のことがやっぱり。この6月26日という日にちが決まってから常に毎日、頭のどこかで1回は猪木会長の顔、名前っていうのが頭の中に浮かびますよね。やっぱり45年間、ここまで成長できたのは自分自身、猪木会長のとてつもない、猪木会長とは違いがあるんですけど、リングの中であの方をずっと見てきて、プロレスっていうものが分かってきてあぁ大変だなこれは、っていうのは、やっぱり常に感じてここまでやってきてますね。でも、それでも、とてもじゃないが、やっぱりリングの中のアントニオ猪木に近づくっていうことは、とてつもなく大変なことなんだなっていう・・・」
「これは本当に終わった時点の中で、この業界でここまでファンの皆さんに支えられながらやって来れたのは、ひとえにあの人を見て、自分なりの感じ方で自分というものは、プロレスは、こういうものだよって。いつまでやるか分からないけど、あの人は教えることはしないですけど、リングサイドから我々には、ここにいる古い記者の人は、多分、知っている通り、猪木会長の場合はあの方が会場の雰囲気を作るというか、ファンの人たちが後押しするわけじゃなくて。やっぱり凄いなって。その時代、マスコミは(ジャイアント)馬場さんと比べたでしょうけど、馬場さんも素晴らしい人でした温厚で」
「でも、自分が選んだのはプロレスの世界ですから、どっちかというと自分の性分からすれば、猪木会長のリングの中の、リングを下りてからも猪木さんの姿勢。本当にこの人、プロレス24時間考えている、やっている、っていうようなことを感じてきましたよね。まぁ到底及ばないですけど、プロレスに大事なものを自分なりに自分なりにこう考えながら、あのリングの中に打ち出してきたんじゃないかなと思っているんですけど、どうなんですかね?やっぱり答えがないですから、でも、その時代の猪木さんは、猪木さんが会場の中を1人で雰囲気を作ってファンを引き寄せていましたよね。ボクなんか現場もやりましたけど、なかなかそこまではできなかったですね。やっぱり凄い方です。はい、そういうことです」
「藤波さんも今日はちょこっと触らせて頂いたんですけど、藤波さんもどっちかというと、ずっと会長に付いてきた人ですから。まぁ表現の仕方は別にして、彼もそうなんじゃないかなと思いますよ。これはボクもちょっと分からないところでしょうね。まぁでも、最後まで本当に悩みましたよ。猪木さんを呼ぼうっていうね。猪木さんを呼んで雰囲気作りをしてもらおうかなっていう部分もありましたけど、今日は最後で自分の集大成としてどういう状況になるのかなって。まぁでも、熱い声援でファンの熱い声援で、リングに押し出してくれて感謝していますよ。はい、以上です。どうもありがとうございました」

そしてリング上では、最後の挨拶でこう語っています。
「私にとってプロレスはなんだったのかなと振り返りますと、すべてが、勝っても負けても、私自身はイーブンです。ホントにイーブンでした。」
長州力らしい回答だな、と思います。
勝った(わかった、という驕り)とも、負けた(できない、という諦め)とも思わない。好き!でも嫌い!でもない。やってやっただろ、とは言わないし、まだまだだな、とも言いたくない。イーブン。
プロの仕事って、そういうものだと私も思います。
<関連記事>
「真説長州力」を読んで感じたこと
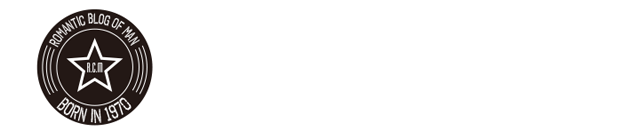
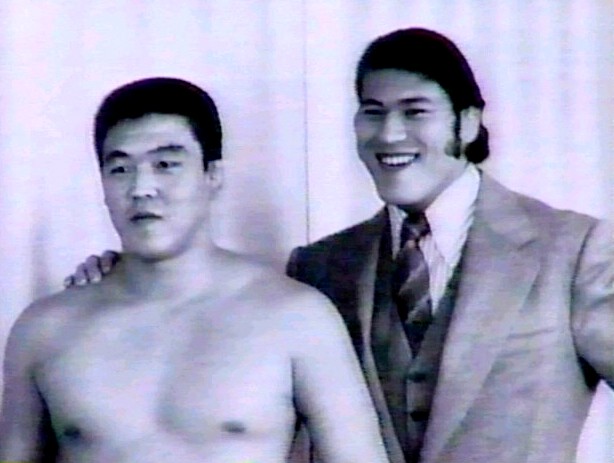

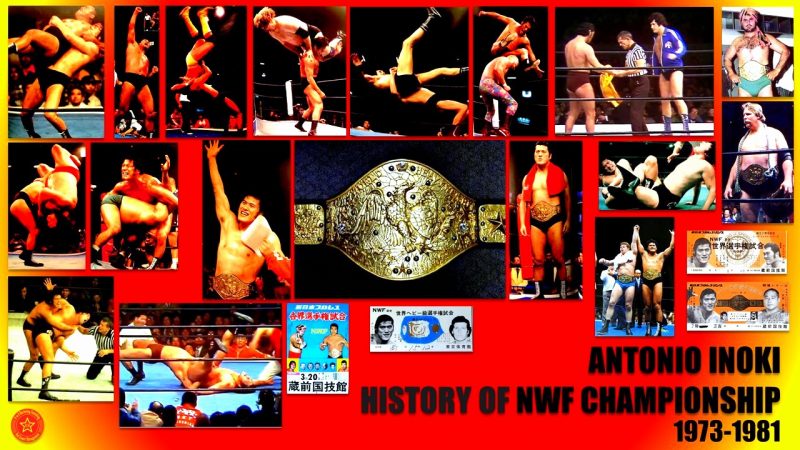
コメント