「海のトリトン」―
私は世代的にリアルタイム視聴者ではなく、残念ながら再放送でも観た記憶がないのですが、あの「有名過ぎる主題歌」と「手塚治虫作品」である、ということだけは知っています。
令和の時代になっても、この「海のトリトン」の主題歌は、甲子園の定番応援曲であり続けています。観客席の高校生に、「この曲が何なのか、知ってる?」と聞いてみたくなります。
>その謎は、こちらで解き明かしています / YouTube番組版はこちら
そして、この「海のトリトン」というアニメ作品が語られるとき、決まって出てくるワードが「最終回のどんでん返し」「トラウマ」というものです。
イルカに乗ったかわいい男の子が主人公で、主題歌からも「海を舞台にした冒険もの」との印象なのですが、いったい何があったのでしょうか。
調べてみると、なるほど、それは衝撃だったでしょうね、というエピソードがありました。
そんなワケで、今回は「海のトリトン」というアニメ作品と、その大どんでん返し、衝撃の最終回についてご紹介します!
アニメ「海のトリトン」とは?
1972年4月1日 〜9月30日
全27話
朝日放送
・原作:手塚治虫
・プロデューサー:西崎義展(テレビアニメ初プロデュース作)
・監督:富野喜幸(現 由悠季/初監督作)
手塚作品を「ヤマト」の西崎氏がプロデュースして、「ガンダム」富野氏が監督する、という濃すぎる揃い踏みによるアニメ作品です。そしてこのお二人はどちらも(プロデューサー/監督として)初体験。
これがこの後の、お二方の作品制作に与えて影響と、後の「打倒ヤマト、打倒西崎の一心でガンダムを作った」(富野氏)の関係性を考えても、非常に興味深いのです。

「私の作品ではない」by手塚先生 とは?
手塚治虫先生ご本人は、秋田書店版の単行本で「テレビまんがのトリトンは自分のつくったものではない」。講談社の手塚治虫漫画全集のあとがきで「自分は原作者の立場でしかない」とそれぞれ、コメントしています。
一体どういうことなのでしょうか。
ここでキーマンになるのが、以前「宇宙戦艦ヤマト」のプロデューサーとして紹介した、西崎義展氏でした。
西崎氏は、ヤマトのプロデュース以前、1971年から「虫プロ商事」に1年数か月間在籍。営業や手塚治虫先生のマネージャーを務めていました。
ちょうどこの頃、「虫プロ」は1973年11月5日3億5千万円の負債を抱えて倒産します。その直前、虫プロ経営悪化による混乱の中、「手塚作品の全アニメ化権利」を手塚先生のマネージャーだった西崎氏が取得します。
おそらくは「売上が必要だから営業してくる。俺に一任してくれ」的なことだったのでしょうか。(後に手塚先生は、「私の今までのすべての版権を西崎に取られてしまった」と悔し涙を流したといいます)
この真っ最中に作られた作品が「海のトリトン」です。
もともと富野氏を高く評価していた手塚先生は「富野氏が監督なら」と、アニメ化を了承したといいます。
富野氏が原作を改変
しかしアニメでは、キャラクターや世界観などが大きく改変されています。見比べててみると、全然違いますね。
その理由を富野氏は「原作がつまらなかったから」と語ってます。
キャラクターデザインが「手塚タッチ」でない理由は、「虫プロ系のスタッフが使えなかったから」(実制作の中心は主に東映動画テレビアニメシリーズの下請けをこなしていた朝日フィルム)で、キャラクターデザインには東映動画出身の羽根章悦氏が起用され、「新しいものに挑む」という基本方針のもと「敢えて手塚治虫調ではないキャラクターを選択した」と言われています。


そして富野氏は、最終回で原作を無視して
主人公トリトン=正義
敵のポセイドン(族)=悪
をひっくり返してしまう、テレビアニメ史に残る衝撃のラストを持ってきます。
見た目に可愛い美少年のトリトンが毎週、海獣をやっつける海洋冒険もの、として(自分が冒険してるかのように)半年間楽しく観ていた当時のちびっこ達の衝撃たるや、いまだに「トラウマ」と語られるレベルなのだとか。
あらすじと最終回
主人公のトリトンは、ポセイドン族によって滅ぼされたトリトン族の生き残りです。
少年に成長したトリトンは何度もポセイドン族に襲われ、その都度、両親から託された「オリハルコンの短剣」を手に、海の平和の為にポセイドン族と戦い続ける…というお話です。
そのアニメ版最終回、トリトンとポセイドン族の最終決戦が描かれます。
そしてラストのラスト、残り半分もないタイミングで、唐突に「勧善懲悪」がひっくり返る事実が明かされます。
かつて、世界にはトリトン族と奴隷のポセイドン族がいて、トリトン族は平和に暮らしていましたが、トリトン族がオリハルコンの神像を造った時、ポセイドン族を人身御供とし、一族を海底の穴に閉じ込め神像で蓋をした。ポセイドン族は、トリトン族によって一方的に絶滅の危機にさらされていた被害者だった。
この辺りの考察は実に多くの方がなされていますが、ものすごく乱暴に言えば、要するに「悪いのはポセイドン族ではなくトリトン族でした」というのです。
そしてさらに、トリトンの持つ「オリハルコンの剣」は、ポセイドン族を皆殺しにするための禁断の最終兵器でした。
その剣の輝きで、海底でなんとか生き残っていた(ほんとは悪くない?)ポセイドン族は全滅。おまけに誘曝させた海底火山のせいで、ポセイドン族の海底都市ごと消えてしまいます。
そしてこの怒涛の大どんでん返しの後、何もかもが全滅したところでナレーション「そして、また、少年は旅立つ…」。そして、あの名曲の主題歌が流れて強引にねじ伏せられて終わってしまうのです。
このラストシーン、「少年はさがしもとめる」「遠く旅立つひとり」の歌詞が、ものすごく重く聴こえます。
なぜこんな最終回に?
いまでこそ「善悪の相対化」はよくみられる手法ですが、この当時は前代未聞でしたし、問題なのはその「やり口」です。
半年間、勧善懲悪で進んでいた物語が、突然、なんの伏線もなく最終回の最後の最後でいきなりコペルニクス的大転回。
時は流れ、当時のリアルタイム視聴者達は、「今となれば言いたいことはわかるけど、それならそれでもっと丁寧にやれよ」と怒っています。
これには理由があり、トリトンは本来1年かけて放送するはずだったのに、これまた当時のよくあるお話で半年で打ち切られたこと。
そしてもう一つ、富野氏は周囲に反対されるのを予測して、スタッフにも直前までこの展開は内緒にしていた、というのです。
富野氏も「あの落としどころだけは、1クール終わった時点ぐらいで思いついていたんですけど、誰にも言いませんでした。だから26話のシナリオは僕が書いているんです」と語っています。
なので何の伏線もなく、最終回で唐突な「ちゃぶ台返し」になってしまったのです。
富野氏と「海のトリトン」
以下、産経新聞の記事から引用します。
実写志望で、リミテッドアニメの手法に違和感も覚えていた富野さんは昭和42年、虫プロを退社。
別の職業を挟んだ後、フリーとなった富野さんが初めて監督を務めたテレビアニメが、サンケイ新聞(当時)で連載されていた手塚漫画「青いトリトン」(海のトリトン)だった。
プロデューサーは、その後「宇宙戦艦ヤマト」を手がける西崎義展さん。富野さんは手塚さんの原作に飽きたらず、西崎さんに「原作、無視していいですか?」と告げて、設定やストーリーに手を加える。
「その仕事が来るまで、本当の意味で自分がオリジナルが好きかどうか分からなかった。単純に海獣をやっつける展開が気に入らなくて、最終回はシナリオなしで勝手に描きました。ライターとはけんか別れして虫プロには出入り禁止になるし、(虫プロのあった)練馬付近にはしばらく近づけなかった」
アニメ「トリトン」のラストでは、主人公トリトンが戦っていた敵の一族が、かつてトリトンの一族と共存していた「仲間」だったことが明かされる。正義と悪の境界が宙づりになる最終話は、今も語りぐさだ。
富野さんのその後の作品には、物語終盤で登場人物の多くが死亡するなどして主人公や視聴者を揺さぶる作品が少なくない。「アトム」と「トリトン」での体験が、富野さんの作家性を培ったといえそうだ。
また、別の対談で富野氏は、
「子供にとって一番大事なことは何だろうと考え、35歳の自分が出した結論は、ともかく嘘はついちゃいけないということだった。それを物語の芯にしようと思ったのね。それが「海のトリトン」という作品だった。」
「原作がひどいと思ったから変えた。そしたら虫プロの先輩たちに袋叩きに遭って、即出入り禁止になった。でも、ガキが海獣に追いかけられてるだけの話で、ただ海獣に勝ちました、パチパチってそんなバカな話、作れるわけないじゃない。だって、そんなことやったら嘘になるから。嘘をつかないためには、僕はトリトンをああいうふうにしか作れなかったんです。」
「なぜトリトン族が二千年も海獣に追われてるかというと、それは二千年の恨みを買ってるからだろう。だとしたらもともとはトリトン族のほうが悪いんだよねという話に、必然としてなるよね。だからそういう話にしたのに、なぜか分からないけど富野はヘンだって言われちゃう。」
引用:富野由悠季×安彦良和対談(ガンダムエース 2009年 09月号)
とも語っています。かなり後年の発言ですので後付け、自己正当化もあるでしょうが。
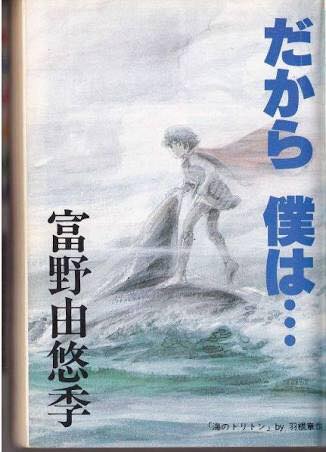
この「海のトリトン」は、初監督作品にして、後の富野作品の特長である「善悪が逆転する衝撃展開」「守るべき民衆に迫害される主人公」「ある意味主人公以上に活躍する脇役」といった特色が顕著であることから、「傑作」との評価を受けています。
手塚先生の原作では、主人公は悪の親玉と刺し違えて死にますが、アニメ版では生き残り、自らの一族の罪を背負いながら生きていく、という終わり方になっています。
「平和は手に入ったが、そこに正義はなかった」
ということですね。終戦を体験した世代としては、悪と刺し違えて死ぬ主人公よりも、取り返しのつかない過ちと業を背負って生き延びる、それで少年が青年に成長していく方が「ほんとう」で、それを子供たちに見せるべきだ、見せたいと考えたのではないでしょうか。
この改変を手塚治虫先生はどう思ったのか、というとよくわかりません(詳しい方がいたら教えてください)。
事実としては「珍しく制作に対してノータッチを貫いた」ということです。原作に「アニメは私の作品ではない」と語ったのは、事実として書いただけなのか、改変されたことへの怒り、忸怩たる思いがあってのことなのか。
これについて富野監督は、「手塚さん本人はトリトンという作品を失敗作と見ていたので、ストーリーの改変などもかなり自由に任せてくれたのではないか」とも回想しています。
富野さんも「リミテッドアニメ」を作る手塚先生には批判的で、クリエイターとしてはライバルでもあるのですが、もともとは手塚先生のマンガを読んで育った世代です。
そこには当然、愛憎が入り混じっていて、
「手塚先生は漫画家、ストーリーテラー、アイデアマンとしてだったら誰にも負けないでしょう。宮崎駿監督より3倍くらい上かも知れません。そんな2人の早書きを見ていたら、僕なんか歯が立たないとわかってしまいます。」
とも語っています。

だから、いつまでも語られる
昭和のアニメには、「子供向けなのにこれ?」という衝撃の展開や、理不尽すぎる「突き放す」ストーリーがよく描かれます。
今どきのアニメのように仲間が死んでもすぐ生き返ったり、絶体絶命になるとすぐに仲間が助けに来てくれたりはしません。クリエイター自身が、そういうご都合主義を『恥ずかしいこと』と捉える感覚が、今よりも強かったように思います。
なので、ものすごく理不尽だったり、せつなすぎたり、「これ見せられてこの後1週間、どう過ごせばいいんだよ・・・」みたいな重い話も、しょっちゅうあった気がします(そもそも主人公が貧乏なのは定番で、「みなしご」ものも多かった)。
でも、私も含めて当時の子どもたちはそれを通じて「なんだか世の中、甘くないな」とか、「世の中にはこっちがどんなに清く正しくても、悪意を持って接してくるイヤな奴がたくさんいるんだ」みたいな、そういった”大人”になる「覚悟」みたいなものを、無意識に学んでいた気がしてなりません。
その理由は、当時の多くのクリエイターたちが終戦という「善悪の大転換」を体験して、その理不尽さに対する怒りが創作の原動力であることや、その後の経済成長とその裏にある格差に対する怒り、そして中には、本当は大人向けの創作がやりたいのに、『ジャリ番』を生業としなければならない己に対してのやり場のない怒りとか、そういうものがある気がするのです。
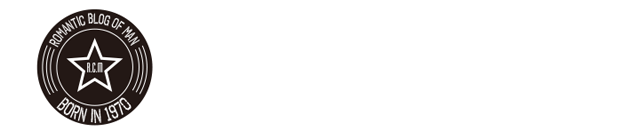



コメント
明らかに富野が悪いだろこんな原作レイプは手塚本人は当時物凄く怒っていただろうな