前回に続き、今回は小林旭さんの「渡り鳥シリーズ」を始めとした日活映画についてご紹介します。

渡り鳥シリーズ
小林旭さんの代表作といえばこのシリーズです。
監督は斎藤武市さん、脚本は山崎巌さん(と大川久男さん)。
① ギターを持った渡り鳥(1959 昭和34年10月)
② 口笛が流れる港町(1960 昭和35年1月)
③ 渡り鳥いつまた帰る(1960 昭和35年4月)
④ 赤い夕日の渡り鳥(1960 昭和35年6月)
⑤ 大草原の渡り鳥(1960 昭和35年10月)
⑥ 波涛を越える渡り鳥(1961 昭和36年1月)
⑦ 大海原を行く渡り鳥(1961 昭和36年4月)
⑧ 北帰行より 渡り鳥北へ帰る(1962 昭和37年1月)
⑨ 渡り鳥故郷へ帰る(1962 昭和37年8月)
1960年は年に4作、61年、62年は年2作というハイペースで公開されているだけでも驚きますが、アキラはこれ以外にも複数の人気主演シリーズがあり、3年間での映画の本数は実に37タイトル!(しかもすべて主演)アキラは超が付く人気者、ドル箱スターになりました。
ストーリーのプロットと、役どころはどれもほぼ同じです。
主人公が小林旭さん、ヒロインが浅丘ルリ子さん、ライバル役が宍戸錠さん。
”ギターを持った流れ者”の主人公が日本各地を訪れては土地の悪者を倒し、ヒロインの苦境(大概が土地の権利書絡み)を救うものの、決して結ばれることはなく去っていく・・・というお話です。
当時流行していたアメリカの西部劇映画をモチーフにしていて、馬に乗って表れて、拳銃の腕前を競い合ったりします(日本なのに)。主題歌も人気西部劇の「シェーン」「ララミー牧場」がモチーフです。
全国の「ご当地」を巡るわりに、どの街でも銀座のようなキャバレー(ナイトクラブ)があり、ダンサー(だいたい白木マリさん)がいて、ダークスーツの悪い連中(金子信夫さんとか)がウィスキーを飲んで(日本酒や焼酎ではない)標準語で悪だくみをしていて、「ここはどこなの」状態(笑)。
その”荒唐無稽さ”から「無国籍アクション」と呼ばれました。
キャストとストーリーが毎回同じですから、舞台となる街が毎回変わります。タイアップで各地の祭や景色が描かれます。
これは、後に松竹の「男はつらいよ」シリーズに引き継がれる手法です。寅さんとアキラ映画の違うことろは、寅さんはご当地のマドンナに惚れてフラれる役回りですが、アキラは惚れられても去っていくのです。(コレを知ると、寅さんの最愛のマドンナがなぜ浅丘ルリ子さんなのか、が理解できると思います)
そしてもう一つの特長が、ご当地の民謡をアレンジした挿入歌をアキラ自身が唄うのです。
「アキラの会津磐梯山」(「赤い夕陽の渡り鳥」)
「アキラのソーラン節」(「大草原の渡り鳥」)
さらにはとうとう海を渡り、東南アジアで撮影された「波濤を越える渡り鳥」では「アキラのブンガワン・ソロ」など海外のご当地ソングまでアレンジ。
これらが「アキラ節」として後のクレイジー・キャッツ、植木等さんに続くノベルティソング(企画モノ)の元祖となります。
>「アキラ音楽編」は別項でご紹介します
キャバレーで悪い連中がヒロインたちをいじめていると、どこからともなくギターと唄声が聴こえて、アキラが階段を降りながら登場。悪い連中は唄い終わるまで手出ししません。このあたりの様式美は、後の仮面ライダーや戦隊モノに引き継がれています。
地方ロケした新作映画がほぼ毎月公開され、それに合わせた主題歌と挿入歌を作ってレコーディングして、封切りの映画館でレコード(ソノシート)が売られて、大ヒットするというビジネスモデル。どんだけ忙しかったのかと思います。
単純にアキラがカッコいい
このシリーズがウケたのは、単純にアキラがカッコいいからです。主題歌と共に馬にまたがって現れ、馬にまたがって去って行く小林旭は、西部劇のさすらいのガンマンであり、時代劇なら怪傑黒頭巾です。
ストーリーもセリフも、「アキラがカッコイイ」だけに徹底してフューチャーして作られていました。
徹底してキザで、ありえないほど強い。
これを一切の照れもなしに、観ている方も恥ずかしくもならずにやれるのが、小林旭さんの魅力です。
私はトム クルーズの映画を観ると、なんとなく小林旭さんの香りを感じます。
「プログラムピクチャー」
前述の通り、「渡り鳥」シリーズがたった4年(実質3年間)で8作も封切られてた合間に別のシリーズも制作、公開されています。
「銀座旋風児(マイトガイ)」(野口博志監督)から続く「旋風児シリーズ」
「東京の暴れん坊」(斎藤武市監督)からの「暴れん坊シリーズ」
「海から来た流れ者」(山崎徳次郎監督)からの「流れ者シリーズ」
と、立て続けに「小林旭主演作品」が制作、公開されていきます。
その理由は「これぞ日活映画のお手本。低予算で、当たる映画。これを手本にしなさい」という日活の方針です。
裕次郎映画が5千万円かかるところを、アキラ映画は3千万円以内。
しかも、1/3近くがロケ地のホテルや観光協会とのタイアップで賄える。
それでいて興行収益は裕次郎映画と変わらないどころか、第5作「大草原の渡り鳥」は興収3億5千万円と年間トップに。
アキラ映画は儲かって仕方がないのです。
小林旭さんの主演映画は
□1959(昭和34)年には出世作となった「南国土佐を後にして」「ギターを持った渡り鳥」「銀座旋風児」など13本
□1960(昭和35)年には「口笛が流れる港町」「海から来た流れ者」「東京の暴れん坊」など12本
□1961(昭和36)年に「でかんしょ風来坊」「高原児」など12本
この3年間は「年間主演本数世界一、現在に至るまで破られていない、前人未踏の大記録」と言われています。
それにしてもほぼ毎月、主演の新作映画が公開されるというのは狂ってます。TVの2時間ドラマでもこんなハードローテーションは考えられませんね(笑)
とにかく、次から次と新作映画を公開しなければならない「プログラムピクチャー」とよばれる時代に、アキラのシリーズ物は最適の企画でした。
海外でも大人気
この時代の日活映画は海を越えて台湾、バンコク、マニラ、香港などに輸出され、中でも人気が高かったのがアキラ映画。
タイでは上映時に観客が主題歌を日本語で合唱するほどで、「波濤を越える渡り鳥」での海外ロケでは各地で熱狂的な大歓迎を受け、パニックだったそうです。
その後も何度もリバイバル上映が繰り返され、香港映画界の巨匠でハリウッドにも進出したジョン ウー監督や、ジャッキー チェンは「マイ アイドル」「サインが欲しい」というほどのアキラファンで知られています。
ジャッキー チェンのアクションは「小林旭さんの映画を参考にした」と本人も語っていて、ジョン ウー監督の出世作「男たちの挽歌」はモロにその結実ともいわれます(主演のチョウ ユンファは「香港の小林旭」と呼ばれました)。

▲どこからどう見てもアキラです(笑)
良識派のバッシング
とはいえ、日活アキラ映画は「粗製濫造」のそしりを受け、いわゆる映画評論家筋の評価は高くありません。
現実離れし過ぎ、バカバカしい、評価に値しない・・・いわゆる”良識派”から”良識的に”猛バッシングされました。
それについて、この時代の日活では、こう言われていたそうです。
「どぶ板社会で生きている客に、どぶ板の映画を作っても誰も見ない」
まだ戦後の焼け野原から、文字通りゼロから生活を立て直していた時代、手の届かないスターの演じるヒーローとマドンナの、夢のようなおとぎ話を観て、苦しい日々の生活を忘れる。それがこの時代の「銀幕」と呼ばれた映画という娯楽の役割でした。
1960年代前半、当時の若者に熱狂的に支持された「大衆の娯楽」。
それが日活アキラ映画でした。
その後のアキラと裕次郎
1960年代前半から日活との契約本数も減らし、自身のプロダクションを立ち上げ他社トップスターとの共演など、新たな道を模索する石原裕次郎さん。
観客が激減するの中でもひたむきにプログラムをこなし、日活を支え続けたアキラ。
日本映画の斜陽化は止らず、1960年代の終わりとほぼ時を同じくして日活は「ロマンポルノ」路線へと舵を切ります。
石原裕次郎さんは1970年代以降は映画を離れ、「太陽にほえろ!」「大都会」などTVドラマで活躍します。
小林旭さんは1972(昭和47)年に東映に移籍。1973年(昭和48年)より「仁義なき戦い」シリーズに出演。その後も仁侠実録路線で別格の存在感を示しました。
おんどれらも吐いた唾 飲まんとけよ pic.twitter.com/Be3BXIoH6s
— 仁義なき戦い 画像bot (@otomo_omeco) December 12, 2019
それからも2人は大スターであり続けましたが、共通して「歌」というもう一つの舞台がありました。
次回は小林旭さんの「唄」の世界についてご紹介したいと思います。
つづきます!
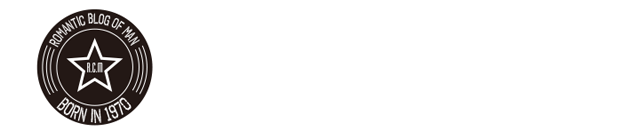



コメント